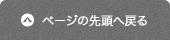研究概要
専門は数学教育協力。先生は日本と海外の双方の研究を行っている。
日本での教育に関しては社会的オープンエンドな問題を取り扱っている。具体的には、数学教育において学習指導要領、つまりカリキュラムの内容や、子どもたちが学んだ内容が身につけたり身につけなかったりという状態を分析的にみる。最初に学習指導要領があり、次にそれに基づいた形で教科書、そして先生たちの教え方があり、それらの結果として子どもたちが身につけるかどうかがつながっていると先生は言う。海外での研究では、10の塊に基づく計算法の取得をテーマとしている。
原点は青年海外協力隊
先生が国際協力に興味を持ったきっかけは、青年海外協力隊としてのフィリピンでの理数科教師の経験だという。先生が見学をした学校の授業では、家庭ではタガログ語を話す生徒ばかりであるはずなのに英語で授業が行われていた。日本の九九のように足し算を英語で唱えていく授業だったという。その授業を見て先生は「この授業は何の授業なのか?算数ではなく英語の授業ではないか?」と疑問に思ったそうだ。このフィリピンでの経験から、数学は言語のようなものであり、それぞれに文化があるという観点に関心を持ち始めたそうだ。それから先生は民族数学(日本でのそろばんや、ある模様の中の対称性など)や数学における社会的側面、ソーシャルオープンエンドな問題を中心に研究されている。社会的オープンエンドな問題とは、社会的な価値観が表れるような問題である。先生は、タイでの例に説明してくださった。例えば、ケーキが5つあり、祖父母、両親、自分、妹で切り分ける際にどのように分けるか、という問題を出す。通常の算数の授業であったら5÷6をする、6の5と分数で表すといった回答が出てくるかもしれない。これらはもちろんすべて正解である。ところが、タイで同じ問題を出した際には、祖父母や両親は子どもより年上で尊敬しないといけないから1つずつ渡し、残った1つを子ども達で分ける、という日本では出なかった回答がでてきた。タイでは目上の人を尊敬するという文化や慣習が根付いているからだそうだ。国によって回答が違うので、そのパターンを見て数学教育の社会文化的側面を理論的に考えることが社会的オープンエンドに関する研究である。「数学は常に答えがひとつに決まるものではない。いろいろな道具として自分たちの経験とつながりあいながら、それぞれの数学の形が生まれるんじゃないか」と先生はいう。
「限りなくわからない」子どもたち

現在、先生はJICAと広島大学が連携しているザンビアプログラムにも携わっている。実際にザンビアに行ったとき、子どもたちが「限りなくわからない」という状況に数多く出くわしてきたそうだ。先生はそれらの例を説明してくださった。日本で分数の計算の問題で2分の1たす3分の1、といわれれば基本的に多くの人が計算できるが、ザンビアの子どもに同じ問題を出すと、書かれているすべての数字を足しだした(1+1+2+3)ことがあった。また、72÷6という問題に対して、棒を72本引いて6本ずつ囲んでいった子どももいた。つまり、そもそも分数や72という数がわかっていないことが判明した。そのとき先生は、「なんなんだろう、このわからなさは?」と関心を持ちはじめたそうだ。
しかし、先生によるとザンビアの子どもたちは「何もわからないというのではなく、ある意味でわかっている、つまり、わたしたちと同じようにはわかってないが、彼らは彼らなりのわかり方をしている」という。例えば、72÷6の計算で線を引いて回答しようとした子どもは、72本引っ張っている意味で72という数をわかっている、72を72番目のものとしては捉えることができている、割り算の意味も理解している。
先生はこの状況を次のように分析する。子どもたちは理解しているが、教師がそれを促進するように授業を行うのではなく、わからなかったら最初から数えてみようという風に授業を行っている。導入レベルだったらその授業は効果があるかもしれないが、さらに理解を促進するための階段をつくるべき教師が「促進」を意識していない。そして先生を教える大学の先生が意識していない。大学の先生や現場の先生がもとにしているカリキュラムがそれを意識していない。このようにつながった問題がここにある。だからこの流れ全体を変えていかなければならず、そのためには証拠となるデータが必要だという。
そこで、先生はこれまでのアプローチではなく、子どもたちは数をどう理解しているのか、計算をどういう風にしているのかを調査して、最終的にはそれに対する処方箋、つまりどのように数学を教えればいいかを分析している。調査では、ザンビア大学の先生方と協力し、10の塊を意識する枠組みを用いる。10のマスが書かれた枠組みに石を置き、その数を数える。こういうと一見簡単なようだが、ザンビアではこの作業を難しく感じる子どもが少なくない。このような子どもたちに枠組みで数を数える練習をする機会を作り、頭の中で枠組みを再現して、それが目の前からなくなっても想起しながら数を正確に数えることができる状況を目指しているそうだ。
先生に数学の重要性を伺うと、「数学は圧縮された言語、そして世界を見たり語ったりする道具である。発展途上国で数学的なものの見方ができないと、科学や技術の発展は望めない。その点で数学は基礎的であり発展的である点から重要である」という回答があった。さらに子どもたちが数学を通して抽象的なものの見方ができるようになるのはとても重要であるという。しかし、初歩的な段階でつまずいている子どもがたくさんいる事実がある。「数学ができなくても困らない、っていう人もいるかもしれない。でも、発展途上国の子どもたちがお金の計算ができるようになり、また国全体で見ても科学技術の進展を国として挙げていく必要がある。そのためには数学の力が必要」と先生はいう。先生はこれからも発展途上国の将来を担う子どもたちが数学を学ぶ環境づくりのために研究を続けられるだろう。
「待つことと期待すること」
学生を指導するにあたり大切にしていることを伺うと、先生は「待つことと期待すること」だと答えてくださった。学生の中には、先生から答えを求めたり、先生の言うとおりにしたりとなかなか自分で努力をする方法をつかめない人もいるという。しかし、先生は個々がそれぞれ工夫して努力した末に、こういう風にすればいいのか、これが大切なのかという「自ら気づく」ことが研究にも必要だという。「つらさもあるが自分がしていてわくわくするような研究を学生にはしてほしい」との思いから、先生は学生に対して大きな方向性は言うが直接的な意見は言わず、学生が自分で考え試行錯誤をする本人の努力を期待しているのだという。これからも先生は「夢を持ち地道に努力する学生」に対して待つことと期待することを続けるのだろう。
馬場先生は学生の指導だけでなく、国際協力研究科長も務めていらっしゃる。研究科長の立場から広くIDECを見ていらっしゃる先生によると、IDECは「既成の枠にとらわれず新しいことに積極的、柔軟に取り組んでいる集団」であるという。来年4月から広島大学では大学院の編成が行われるが、21世紀という変革の時代において伝統や慣習にとらわれず柔軟に取り組んでいくIDECは大学院編成後もその特徴は存在感を残すことだろう。
最後に、国際協力分野へ関心がある高校生・大学生に対して、次のようなメッセージを送ってくださった。
「21世紀になって、すでに20年が過ぎようとしています。今年はオリンピックも開催されます。そのような中で、これから大きな変化が表れてくることが指摘されています。予想できないという意味で、変化することは怖い部分でもあります。けれども若い皆さんの柔軟な発想で、ぜひいい形にかじをとってください。国際協力は否応なしにもさらに必要となるでしょうが、みなさんのしなやかな感性が必要になってきます。」

馬場 卓也 教授
ババ タクヤ
教育開発コース 教授
主な経歴
1984年7月-1986年12月 青年海外協力隊、フィリピン
1987年4月‐1991年3月 大阪府高校教員
1991年7月‐1995年12月 JICAケニアNYS技術学院プロジェクト、専門家
1999年4月‐2000年3月 JICAケニアSMASSEプロジェクト、専門家
2001年07月-2003年09月 広島大学, 大学院国際協力研究科教育コース, 助手
2003年10月- 2009年3月 広島大学, 大学院国際協力研究科教育コース, 准教授
2004年04月- 2005年03月 文部科学省, 日米理数教育比較研究会, 委員
2004年09月-2005年03月 筑波大学, 教育開発国際協力研究センター, 客員研究員
2009年4月- 広島大学, 大学院国際協力研究科教育開発コース教授