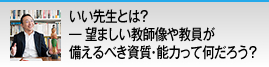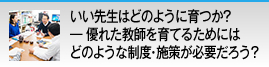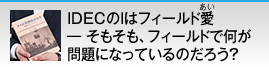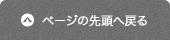研究の概要と対象地域
牧先生の研究室は教育人材開発論研究室。教育開発に資する人材をいかに育てるか、比較教育学、教師教育の視座からアプローチしている。
タイに関心を持ったきっかけは、学部2年の時に、日航財団主催のアジア・太平洋の大学生と交流する短期交流プログラムに参加したこと。その後、熊本県内のNGOがタイに派遣する日本語教育のボランティアを募集しているのを知って応募し、メコン川沿いにある中等学校に2か月間行ってきたことが、さらにアジアへの関心を強くしたという。
「タイの子ども達にとって学校はすごく楽しい場所。先生たちも楽しそうだったんですね。国際協力というと途上国と先進国という区分けがよくされるんですが、私自身は特にそうした思いがなくて、自身のタイでの経験から、むしろタイから日本が学ぶことがあるのではないか、というのが元々の研究スタンスとしてあります」と牧先生。
「これまで行われてきたタイの学校教育についての研究では『教師の質に問題』と指摘されてきましたが、教師の問題についてはなかなかまとまった研究がなされてこなかった分野なんですね。しかし、教育改革を進めているタイでは、教員というのは一番要の部分ですからね。そんな想いからこの研究を続けています。」今後は、タイから、教育開発コースとつながりのある隣国のラオス、ミャンマー、カンボジア、ザンビア、マラウィ、ルワンダへと研究の対象を拡げたいと語る。
専門領域: 比較教育学、教師教育 Comparative Education, Teacher education
いい先生とは?
― 望ましい教師像や教員が備えるべき資質・能力って何だろう?

先生は、教員の研究を2つの観点から行っている。ひとつは、いい教師の条件とはどんなものか。ふたつめは、いい教師を育てるにはどういう制度設計・施策が必要かというもの。
ひとつめは「いい教師」の条件について。担当している授業の受講生や、JICAの研修で来日している研修員に「いい教師ってどんな教師」と尋ねるようにしているという。日本人学生からは「優しい先生」「怒るのではなく叱る先生」といった答えが返ってくる一方、留学生の多くからは「子どもたちに試験でいい成績をとらせることができる先生」という答えがしばしば返ってくる。
そこで、牧先生は問いかける「皆さんの恩師ってどんな先生だった?」と。そうすると、留学生からの答えは先ほどとは違って、日本人学生と似たような回答が出てくる。「実に、面白いですね。」と牧先生。
これの、何が、どこが面白いか?」それは話の続きを聞いて下さい(笑)「究極的に、いい教師というのは人によって異なる主観的な存在。ただ、そう考えてしまうと、いい教師というのは生まれるもので、育てることはできない(teachers are born, not made)ということになってしまいます」ちょっと遠回りになってしまうのですが「世界の学校掃除」という研究があると牧先生は続ける。
みなさんも経験があると思いますが、小学生、中学生、高校生になっても学校の掃除をした経験があるはずです。日本人学生や東アジア、東南アジア諸国からの留学生は、学校掃除したことあるって答える場合がほとんどです。では「なぜ、日本も含むアジア諸国では、児童・生徒が学校掃除をするのでしょうか?」と牧先生。

訪問先の小学校(タイ・バンコク)
「その昔、仏陀の弟子にチュラーパンタカ(別名 茗荷)という者がいたと言われています。チュラーパンタカは、物覚えが悪く、3年間修業を積んでいるがいっこうに悟りを得ることができなかった。仏陀は、チュラーパンタカに一本の箒(ほうき)を渡し『塵を去り、垢を除こう』と唱えよと諭された。
そして、チュラーパンタカは、毎日、この訓(おしえ)の一句を唱え、箒で掃くうちにある日『塵とは心の塵、垢とは心の垢、修業とはこの心の塵と垢との迷いを除くことである』と悟った」という説話が残されています。
この説話からは、ひとつには、学校掃除は人間形成と深い関わりがあること、ふたつには、人間が成長するためには、誰かの(大人の)手助けが必要なこと、つまり、人間の発達への助成的介入としての教育の必要性であり、教師(教職)の存在意義。そして、みっつには内田樹氏が書いているように「優れた教師」は「学習者の主体性」によって決まる、ということです。優れた教師について考えるヒントは、この3つ目にあります。この点について、先ほどの説話を用いてもう少し深く考えてみましょう。
そもそも仏陀は、チュラーパンタカに箒で掃く、すなわち掃除をすれば悟りが得られる、と説いて(教えて)箒を渡したわけではありません。チュラーパンタカは「塵を去り、垢を除こう」と唱えながら箒で掃くこと通じて、仏陀は何を伝えたいのか、と問い続けたのです。
そして、その答え、すなわち「箒で掃くことで、心の塵や垢がとれて悟りを得る」ということに「自分で気づいた」のです。にもかかわらず、チュラーパンタカは、仏陀に箒を渡されたこと、すなわち仏陀の教え、導きによって悟りを得ることができた、と信じ切っていたんですね。こうした学習者の主体性によって、優れた教師は、姿を現したり、隠したりします。「(優れた)教員は生まれるものであって、造られるものではない(teachers are born, not made)」と言われるわけです。
仏陀のみならず、かつて和辻哲郎氏が世界の四聖として挙げた仏陀、そして、孔子、ソクラテス、イエスも同じように、学習者(弟子、後継者)の主体性により、また、その弟子、後継者との(死後も続いた)対話を通じて、優れた教師となったのです。

訪問先の中等学校(バンコク・タイ)での聞き取り調査
同様のことは、みなさんにとっての恩師、みなさんが考える「いい教師」を思い出して、その先生の特徴についてまわりの人と意見交換を行ってもらえればよく分かります。Aさんにとっての「いい教師」は、必ずしもBさんにとっての「いい教師」ではないのです。このように考えると、優れた教師は、個々の児童・生徒の主観的な存在であり、個々の児童・生徒によって優れた教師の条件は異なるということになります。
このように考えると、どのような施策を講じれば「優秀な教師」を育てることができるかなどわかりません(どのような施策を講じても結局、学習者次第だからです)。ちゃんちゃん♪
これでは、教師教育は要らないということになってしまいます。
もう一度、よく考えてみましょう。実は、先ほどの四聖に限らず、みなさんの恩師すなわち「いい教師」、「優れた教師」には、一つの共通する特徴を見出すことができるのです。それは、学習者が「畏れ」を抱く存在だということです。先ほどの内田樹氏の言葉を借りれば、学習者が「(この先生は)何だかよくわからない人」だと感じて、強い興味・関心を持ち、また同時に「先生の中には、私には決して到達できない境位がある」あるいは何かを追い求めていて「ある種のみたされなさに取り憑かれた人」だと実感するような存在ということです。
この点において、先に挙げた仏陀、孔子、ソクラテス、イエスといった人類の教師は、いずれも真理を追い求めていた「ある種のみたされなさに取り憑かれた人」でした。その真理探求の過程は、学習者(弟子、後継者)にとって「私には決して到達できない境位」として映ったに違いありません。ここに、主観的存在としての教師と客観的存在としての教師が備える資質・能力の重なりを見いだすことができます。
すなわち「探究心」です。客観的な存在としての学校教員に求められる資質・能力ないし力量の具体的な中身については緒論ありますが、優れた教師の資質・能力の核心は、今津孝次郎氏の言う「教職自己成長に向けた探究心」であると考えています。この探究心こそが、その他の資質・能力の原動力なのであり、主観的存在かつ客観的存在としての「優れた教師」を存在せしめる鍵なのです。
いい先生はどのように育つか?
― 優れた教師を育てるためにはどのような制度・施策が必要だろう?

ふたつめの観点「いい先生はどのように育つか?―優れた教師を育てるためにはどのような制度・施策が必要だろう?」について。みなさんの中には、この問いに対してすぐさま学校教員に対して各種のしかるべき研修を行えばよい、教員養成カリキュラムを改革すればよい、あるいは、給与を高めればよい、教員を評価すればよい、といったような施策―昨今、日本で導入・実施されているような種々の施策―を思い浮かべた方もおられると思います。
では、近代的な学校教育制度が整備された初期の頃(1900年代頃)から、今日至るまで、折に触れて言及される「(優れた)教員は生まれるものであって、造られるものではない(teachers are born, not made)」という言葉をどう捉えたらよいでしょうか。
この言葉は、学校教員の質をいかに高めるかという手段を模索する者にとって、少々高い壁です。このような優れた教師をいかに育てるか、といった手段ばかりに囚われる発想は、最も大切な事柄についての吟味が欠けています、と牧先生。大切な事柄とは何でしょう?
それは、ひとつめの観点として取り上げた、そもそも「優れた教師」とはどのような人間であるのか、より専門的に言えばどのような資質・能力ないし力量を備えた教師が優れていると言えるのか、という教師教育の目的の吟味です。
ふたつめの観点については、すでに、これまで行われた研究によって、教員養成課程への優れた学生の選抜・養成のカリキュラム・採用・配置・研修・報奨という次の6つの領域にわたって教師教育の制度・施策を考えることが大切だと言われています。言い換えれば、これら6つの領域が育てたい教師像に向かって一貫性をもって整備されていること、グランドデザインが大切だということです。
牧先生は、前述のようなタイでの研究を主軸としながら、カンボジア、ラオス、ミャンマーといったタイ周辺のアジア諸国、さらには、アフリカのザンビアやマラウィ、ルワンダなどでも、教員という切り口で研究を拡げていきたいと考えている。
実際に、国ごとに見ていくと、教師をとりまく状況はさまざまで、国によって教師の仕事内容にも多様性が見られるため、それぞれを比較する中からまた、新たな発見が得られると期待する。例えば、アジア各国の文化や制度が急激に変わってきたここ10年に注目して、それぞれの教職の専門性がどのように変化してきたのかを調べた結果は、『アジアの教員 変貌する役割と専門職への挑戦』という本にまとめられている。また先生は、「日本の教員養成システムというのは大変よくできている」と語り、調査先でも自身の日本で得た知見を発信しつつ、現地と関わっていくよう努めているという。現地との関わりにおいて、先生が大切にしているのは「フィールド愛」とも呼ぶべきものだ。
IDECのIはフィールド「愛」
― そもそも、フィールドで何が問題になっているのだろう?

今日、学校、教員、授業、児童・生徒といった日本語が指し示すものは、国内外を問わず、比較的簡単に見つけることができます。
それぞれの国の学校を訪ね歩けば、学校の校舎や校庭、授業を行っている教員、それを聞いている児童・生徒といった、日本の学校に似た風景を見つけることは難しくありません。このような学校教育、より正確には、近代的な学校教育制度は、いわゆる先進国や途上国を問わず、遍く世界中に浸透しつつあります。
こうした近代的な学校教育制度の下では「学校は教師次第(as is the teacher, so is the school)」という言葉が端的に示すように、学校教育と教員は分ちがたいほど強力に、そして密接に関係しています。
例として、日本の場合を考えてみましょう。学力問題をめぐる論争が端的に示しているように、学校教育の質が問題にされる時、あるいは学校における様々な事件が問題にされる時、必ずと言ってよいほど教員の指導力や事件への対応、日頃の言動などについて言及されます。
逆に言えば、教員に言及しなかった場合、学校教育をめぐる諸問題を取り上げたことにならないに等しいほど、教員と学校教育は強く結びついています。確かに、学校教育の質の向上を考える際、教員の質の向上は必要不可欠です。しかし、学校教員の質の向上だけでは十分ではありません。
学校教育の質を支えている要素は、教員だけではなく、たとえば、教育内容や教育方法、学校の施設・設備等の整備など多岐にわたっています。
ちなみに、私が、学校教員の研究に取り組むようになったのは、単に、学校教育の質を左右するという理由からではありません。そもそも「私は、学部生の頃は国際関係論の研究室に所属していて、卒論はタイの政治がテーマだったんです。その中で、1960年代には国家開発の手段として学校教育が大変重視されていた。それで次第に学校教育に関心がシフトしていきまして、大学院の後半からタイの教師教育改革を扱っています。」
つまり、教師教育ではなく、カリキュラムが問題になっていたらそれを研究していたと言い「現地のホットイシューに焦点を当てる」とのこと。
これまで見てきたように、先生の研究の切り口に「教師」と「比較」があるが、これにもうひとつプラスされるのが、「フィールド愛」つまり「フィールドについての全体理解」という観点だ。これは、現地で問題になっていることに合わせて研究をしていくという先生の基本姿勢とも言えるもの。
「教員のことを知るには、教員のことだけではなく、歴史や文化や社会状況などトータルになんでも知ることで、教員をめぐる様々な事柄の理解に大いに役に立ってくる。全体を理解することの重要性はそこにあると思っています」と先生。
その結果、学校教員以外にも研究は広がっていき、タイのコミュニティ・カレッジや社会福祉などについての研究成果もまとめられている。また、最近はアジアの大学入試と高大接続についても研究を進めているという。このような研究スタイルがとれるのはフィールドの言語をある程度習得しているからこそできることだと言う。

訪問先の国家教育試験機構(タイ・バンコク)での聞き取り調査
「うちのゼミ生には現地語ができるようになることを求めています。現地調査ではとにかく信頼関係が大事なんですね。
相手が建前を言っていないかどうか、嘘をどうやって言わせないようにするか、ぼそっと言った本音を拾えるかどうか。彼らの本音に迫るために現地語が必要なんです」と先生は言う。
そのため、ゼミはバイリンガルであり、基本の英語に加えて、タイを扱うときにはタイ語で、カンボジアの場合はクメール語で会話をするという風なことが往々にして行われている。
対象地域が広がるほどに、フィールド愛も膨らんでいき、言語学習だけでも大変な苦労となるが、こうした研究手法を今後も貫いていく計画という。
ちなみに、留学生が約7割のIDEC、牧先生のゼミに学ぶ留学生は、日本語のシャワーを浴びている。「帰国後も、サバイバル程度でよいので、日本語で話ができる(日本の文化に理解のある)学生を育てたい」という。

訪問先の小学校(タイ・バンコク)
さてここで、広島大学に赴任して2年目という先生は、IDECでの活動についてどのように捉えているのかを尋ねてみた。すると、「一般に、大学では、自分の研究してきたことが学会のひとつの知見になるという、ある意味、謙虚な研究のあり方に重きがおかれているように思いますが、IDECでは自分の研究したことが実際に現場で生きていくんですね。そういった実践より、フィールドよりなところが、ここでの研究の特徴であり、おもしろさのひとつだと思います」と語り、自身の研究活動と教育活動がうまくリンクできる場所になっていると明言。
「私の研究は、その国・地域について理解して、あれこれ考えて、現地にフィードバックするのがひとつ。さらには、日本だとこう、あの国だったらこうというような国際比較の視座から得られる知見を対話を通して加えていくもの。そこには現地の人々の協力も欠かせません。こうした活動はまさしく国際協力。IDECで研究する意義を実感しています」と微笑んだ。
最後に、IDECでの学びを考える学生に向けて、先生はこの研究科の魅力を次のように挙げてくれた。
「ひとつは、『モチベーション4.0』。キャリアアナリストのダニエル・ピンクの本に『モチベーション3.0』というのがありますが、それによると、モチベーション1.0は生理的なもの、2.0はしないと怒られるというもの、3.0は自律的なもので、多様な学生が集まるIDECでは、これにプラスして、『モチベーション4.0=研究せずにはいられない』というものがあると思います。「研究が私の食事である」そんな学生に来てほしいです(笑)

もうひとつは、『国際協力マインドとネットワーク力』。国際協力には知識や技術も必要ですが、一番大事なのは信頼関係。これこそが国際協力マインドであり、多様な学生・教員が集うIDECは日本に居ながらにして国際協力マインドを育むことができる国際的な環境です。そして、IDEC在籍中に培った信頼関係が、修了後はネットワークとして活きる。今も海外の調査研究では、多くの修了生たちがを私たちの教育、研究活動を助けてくれる。その力はとても大きいですね。」


牧 貴愛 准教授
マキ タカヨシ
教育開発コース 教育人材開発論研究室 准教授
2006年4月1日~2008年3月31日 日本学術振興会・特別研究員(DC2)
2006年8月1日~2007年3月31日 タイ王国 教育省教育審議会事務局・訪問研究員
2008年4月1日~2010年3月31日 熊本大学大学院 社会文化科学研究科 (教授システム学専攻) 特定事業研究員
2010年4月1日~2011年3月31日 広島大学大学院 教育学研究科・教育研究補助職員
2011年4月1日~2012年3月31日 広島大学大学院 教育学研究科・助教
2012年4月1日~2014年8月31日 別府大学文学部(教職課程)・講師
2014年9月1日~ 広島大学大学院 国際協力研究科・准教授