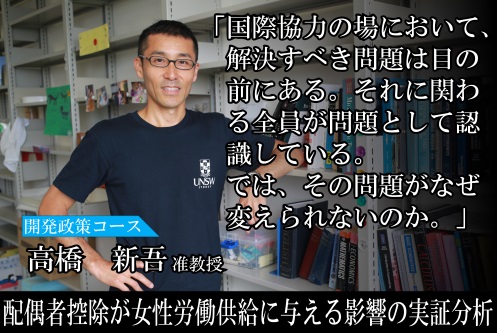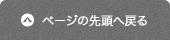研究概要
高橋先生の専門は経済学。特に、「労働・働くということ」に関する諸問題を検討する「労働経済学」を専門としている。労働経済学は、ミクロ経済理論の一分野で、現実のデータに基づき労働参加の意思決定といった人々の行動を読み取る。労働経済がカバーするトピックは幅広いが、そのなかでも、先生は人事制度の研究や、配偶者控除と女性の労働供給に関する実証分析、主観評価に関する実証研究を行っている。
「研究を行っていると、実際の政策上の議論で当然と思われていることでも、研究の結果からは正しくないとわかることがある。労働経済学者は労働政策に直結する研究をしているから、よりよい政策議論に研究者は貢献できるのではないか」と高橋先生は言う。
専門領域:計量経済学、労働経済学
配偶者控除は女性労働供給にどのような影響を与えているのか?

収入の無いまたは少ない配偶者がいる場合に与えられる「配偶者控除」の制度。現在、この「配偶者控除」の是非をめぐる議論が続いている。
給与としてお金を稼ぐと、何パーセントという形で所得税がかかる。しかし、税金の計算は給与にパーセントを掛けて計算するのではない。給与から「控除」を差し引いた「課税所得」に対して何パーセントという形で所得税が計算される。
だから、「控除」の額が多いほど払う税金は少なくなる。
「配偶者控除」はそのような控除の一つだ。収入の低い配偶者(多くの場合は妻)がいる場合は、家計の主な稼ぎ手(多くの場合は夫)は配偶者控除をもらえる。支える家族が多くいる家計の税額をへらし、家計を少しでも助けようという制度だ。以下、収入の低い配偶者を妻とし、主な稼ぎ手を夫として話をしよう。この配偶者控除だが、妻の年収が103万円以下の場合、夫は38万円の配偶者控除をもらえる。妻の年収が103万円を超えると、妻の年収が増えることに1対1の関係で配偶者控除は減らされ、妻の年収が141万円になると配偶者控除額はゼロになる(実際は、103万円以降は配偶者特別控除という名前になり、夫の課税所得が1000万円以下の家計のみに当てはまるが、大部分の家計はこれに当てはまる)
つまり、妻の年収が103万円を超えると、妻が1万円稼ぐごとに、夫の課税収入が1万円増えるということになる。夫の税率が20%だとすると、妻が1万稼いでも夫の税金が2千円増えるので、家計に入るお金は8千円のみになる。だから、妻の立場からすると、103万円を超えたところで、税率が20%になったことになる。労働経済の理論からいえば、103万円を超えた時点で労働意欲が減退するはずだ。これが、「配偶者控除制度が女性の労働供給を抑制している」といわれる理由だ。
ただ、労働経済学では、「理論的に労働抑制効果がある」と言うことと同じくらい重要なのは、「その理論がデータに支持されているのか、そして支持されているとしたらその抑制効果がどの程度なのか」ということだ。これは、データを使って実証するしかない。
そこで、データを使って構造推定と呼ばれる方法をもちいて、既婚女性の労働供給のパターンを調べたところ、配偶者控除制度を完全に撤廃したとしても、労働供給が増えるのは限られた一部の女性のみで、増え方も4%程度。全体としてみたら、0.7%しか労働供給が増加しないことが分かった。「女性の労働参加を阻害している大原因」として議論されることの多い配偶者控除制度だが、それから程遠いほど小さな効果だ。配偶者控除制度は減税制度。労働抑制効果があまりないのに、これを廃止してしまったら単なる増税になる。
「理論的に言えば、配偶者控除には労働抑制効果がある。しかし、本当に、配偶者控除を撤廃するだけで女性の労働が急激に上昇するかということを見たかった」と先生は語る。実際に語られていることが本当に正しいのかどうかを究明するという先生の研究への情熱がこの一言から感じられる。「ここ最近、(配偶者控除の)壁が少し変更されたので、またデータを取って分析してみたい」と今後の研究課題についても語ってくれた。
研究の道へ進むきっかけ
研究への情熱を穏やかに語る高橋先生は、どんなきっかけで研究の道に進むことになったのか、先生の歴史を少し語ってもらった。
「周りの先生たちは大学生の頃から研究者になりたかったのかもしれないけど、僕はどっちかというと、そういうタイプではなかった」と笑いながら楽しそうに語る。
最初に留学したのは、オーストラリアだった。大学附属の語学学校から修士課程に進学した時、有名な大学の先生のもとで学んでいた博士課程の友人と先生は出会った。「彼と勉強していると、修士だけだと理解が浅く、全然理解できていないと感じることがあった。自身がいかに何もわかっていないのかが身に染みた」と当時の経験を回想するように先生は語る。それが、アメリカのノースキャロライナ大学に移り、博士課程に入るきっかけになった。
そこでさらに、どのような時に理解が浅いなと自身で感じたか、先生に詳しく尋ねてみた。先生は、「論文を読んでいてもほとんど理解できなかった。これは僕が知らないもっといろんなことがありそうだなと思った」という。ひたむきに勉強を続けているうちに、自分の仮説と、自分の推定が一致したりするようになったそう。そして、「パズルを解いてるような楽しさがあった」と経済学の楽しさを知ったという。ひたすら勉強したことが学問の楽しさを高橋先生に気づかせ、研究者の道に進むきっかけになったようだ。
学生を育てるということ

教員はものを教えてあげるという立場にいてはいけないと高橋先生はいう。
国際協力研究科にはたくさんの国から学生が集まって来ている。そのような環境の中で、先生自身も学生から学び、吸収したいと話す。
とりわけ、国際協力研究科には、発展途上国から多様なバックグラウンドをもった優秀な学生が学びに集まっていて、卒業後には自国の発展に貢献はずだ。しかし、「国の発展の度合い=その国の人材の優秀さ」ではないという、全く当然のことに気が付いた。IDECに来る学生は一流の能力を持った学生ばかりだ。そして、その大部分が発展途上国からきている。つまり、優秀な人材がいたとしても、国は発展するとは限らないという現実がある。それは一体なぜなのか。優秀な人材の能力を阻害するものが必ず存在し、それを理解する必要がある。このことに関して、現地から来た学生の方がより詳しく知っているし、学生から私自身も学びたい」といい、先生は学生とともに学ぶ姿勢を大切にしている。
さらに続けて、学生には能動的に授業に参加し、積極的に学習してほしいと先生はいう。「先生がしゃべっているだけでは、学生もつまらないし学べない。学生が大学の先生を突っつくくらいの方がいいんじゃないかと思うんですよね。その方が僕もうれしいんですよ。本当は、僕が学生の質問から逃げられないくらい質問してほしいですね。」と先生はにこやかに学生への期待を語ってくれた。
インタビュアーから一言

「国際協力の場において、解決すべき問題は目の前にある。それに関わる全員が問題として認識している。では、その問題がなぜ変えられないのか。その背景を正しく理解する必要がある」と先生。
発展途上国にとどまらず日本にも、様々な問題が残っている。先生が言うように、そういった問題は解決すべき「問題」として多くの人々に認識されている。しかし、その問題は長年解決されずに依然として存在している。それはなぜだろうか。
そういった問題に対して様々な人が多様な意見を述べている現在。あたかも正しいかのように様々なことが語られている。果たして、正しいことが語られているのだろうか。
私たちは学生である一方研究者の卵である。私たちも、研究から得られた結果を踏まえて何が正しいかを明らかにしていかないといけない。
そのように、高橋先生との対話から研究の意義を改めて感じた。
記事作成:内田涼【平和共生コース】
高橋 新吾 准教授
タカハシ シンゴ
開発政策コース 経済学・「労働経済学」研究室 准教授